【連載コラム(全2回)】定額減税の仕方をわかりやすく解説(1/2回目)

|
本日から全2回にわけて、定額減税の仕方やポイントになりそうなところを解説していきたいと思います。
各回の内容としては
1.定額減税の概要
2.減税のしかたと減税しきれない場合の対応
について解説したものになっています。
今回は、定額減税の概要について解説いたしますので、ぜひ最後までお読みになってください。
● 定額減税の概要
では、まずは、定額減税の概要からご説明いたします。
定額減税とは、以下の対象者一人につき、所得税が3万円、住民税が1万円の「合計4万円」を減税するというものになります。
<対象者>
・本人
・同一生計配偶者(合計所得が48万円以下の方)
・扶養親族
例えば、本人と、年収103万円以下の配偶者と、子どもが2人いたと仮定します。
その場合は
所得税:12万円(=3万円×本人、配偶者、子ども2人の計4人分)
住民税: 4万円(=1万円×本人、配偶者、子ども2人の計4人分)
の「合計16万円」が減税される、ということになります。
ここで、扶養親族の人数のカウント方法について、一つ注意点があります。
それは
16歳未満の方も人数にカウントする
ということです。
所得税を計算する上では、16歳未満の方は扶養控除の対象とはならず、その人数によって税額が変わるといったことはありませんでしたが、今回の定額減税については、16歳未満の方も人数にカウントします。
つまり、16歳未満の方の人数によって定額減税の金額も変わるため、給与計算をする上では 16歳未満の方の人数も、しっかりと把握しなければなりません。
また、配偶者については、生計を一にし、かつ、合計所得が48万円以下(給与収入だけなら年収103万円以下)の方でないと、定額減税の対象者とはなりません(職員の所得税が減額されることはありません)。
合計所得が48万円を超える方は、配偶者自身が減税の対象となりますので、
ご自身がお勤めの会社で、ご自身が受け取る給与にて
ご自身が定額減税を受けることになります。
給与計算を担当される方は、しっかりと覚えておきましょう。
第1回目の内容は以上となります。

ここまで、お読みになって「なんだか大変そうだな」と思われた方、ご安心ください!
プロテックの「SimWork給与計算システム」なら、安心して定額減税の準備から、給与計算、年末調整まで対応できます。
また、Xやメールマガジンでも様々な情報を配信しておりますので、そちらもぜひフォローしていただけると励みになります。
次回は「2.減税のしかたと減税しきれない場合の対応」について解説いたします。
それではまた、次回のコラムでお会いしましょう~!
※本コラムは、定額減税のしかたをわかりやすく解説することを目的としたものであり、妥当性や正確性を有すること、 およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
詳細については、国税庁の「定額減税 特設サイト」をご覧ください。
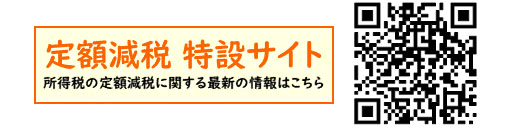
|