【連載コラム(全2回)】定額減税の仕方をわかりやすく解説(2/2回目)

|
今回は、減税のしかたと減税しきれない場合の対応について解説いたします。
ぜひ最後までお読みいただけるとうれしいです。
第1回目については
こちらです。

● 減税のしかた
第1回目のコラムで、定額減税は、
対象者一人につき、所得税が3万円、住民税が1万円の「合計4万円」を減税するものであることを
解説いたしました。
このうち、所得税の定額減税については、
令和6年6月1日から12月31日までの期間、職員に給与や賞与を支払う際に
「源泉徴収税額」から「定額減税額」(=3万円×人数)を控除する
かたちで減税されます。
例えば、定額減税額が本人のみの「3万円」で、6月の減税前給与が以下のとおりだとします
(金額はわざとわかりやすい金額にしています)。
<6月給与(減税前)>
月給 :300,000円
社会保険料 : 50,000円
源泉徴収税額: 5,000円
住民税 : 0円
――――――――――――――――――――――
手取り金額 :245,000円
所得税の定額減税は、定額減税額の3万円に達するまで、源泉徴収税額から順次控除していくことで減税されますので、減税後の給与は
<6月給与(減税後)>
月給 :300,000円
社会保険料 : 50,000円
源泉徴収税額: 0円(5,000円→0円)
住民税 : 0円
――――――――――――――――――――――
手取り金額 :250,000円
となり、本来は手取り245,000円だったところ、5,000円が減税されて、
減税後の手取りは「250,000円」になる(職員が受け取る給料が5,000円増える)ということになります。
また、この職員の場合、
まだ「25,000円」(=定額減税額3万円-既に控除している5,000円)を減税できますので、
7月も同様に5,000円を控除、8月も5,000円を控除、9月も5,000円を控除…と
定額減税額の3万円に達するまで順次控除していき
3万円まで控除しきったあとは、減税前の手取り金額に戻る、ということになります。
● 減税しきれない場合の対応
ここまでお読みになって、では、そもそも給料(源泉徴収税額)が少ない方や、扶養親族の人数が多く定額減税額が高額になる方などは、
令和6年中に支払う給与から控除しきれずに残ってしまった分はどうなるの?
と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
大丈夫です、ご安心ください。
控除しきれない場合は、年末調整で所得税額の精算を行って、それでも控除しきれない場合は、
給付金という形で調整が行われる見込みです。
皆さん、毎年1月に、源泉徴収票や給与支払報告書といった書類を管轄の税務署や市町村に提出されているかと思いますが、 控除しきれない場合については、これらの書類のデータを元に市町村が給付金を計算して調整を行ってくれる、という流れになります。
ただ、いくら給付金の計算は市町村側が行ってくれるとはいえ、
市町村は、源泉徴収票に記載されている金額を見て、
控除しきれなかった分の給付金があるのか否かのチェックをかけますので、
源泉徴収票が間違っているとその後の給付金の計算も間違ってきます。
なので、今年は特に給与計算のミスや年末調整の間違いがないように気をつけましょう。
なお、住民税の定額減税については、市町村の方で計算しますので、会社側で何か計算をするといったことはありません。今年も5月頃に、 6月から来年5月までの各月に天引きする金額が記載された「特別徴収税額通知書」が市町村から送られてくる見込みですので、 そちらに記載された金額を天引きしていただければ問題ありません。
※給付金については、市町村の事務負担などを踏まえ、差額を1万円単位で給付するルールになる見込みです。
※今年に関しては、市町村の事務処理が間に合わないということもあり、6月の給与から天引きされる住民税は全員一律で0円となります。
第2回目の内容は以上となります。

ここまで、お読みになって「給与計算や年末調整のミスが心配だ」と思われた方、ご安心ください! プロテックの「SimWork給与計算システム」なら、安心して定額減税の準備から、給与計算、年末調整まで対応できます。
また、Xやメールマガジンでも様々な情報を配信しておりますので、そちらもぜひフォローしていただけると励みになります。
それではまた!
本コラムは、定額減税のしかたをわかりやすく解説することを目的としたものであり 、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
詳細については、国税庁の「定額減税 特設サイト」をご覧ください。
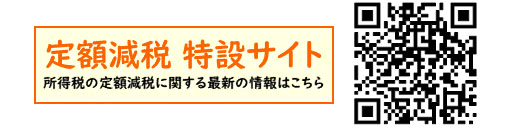
|